私、料理が苦手で0歳の息子がいる32歳の主婦です!
料理が苦手です! 毎日面倒臭くて、もっと楽に、美味しくできる方法ないかな?
ここでちょっと言いづらいけど、私は料理が好きな35歳主婦、2歳の子供がいます!
料理が好きでも、面倒臭くなるときは多々あるし、もっと楽しく簡単に料理をしたい!
そんな人にはぜひ、「蒸篭(せいろ)」をおすすめします!
え、蒸篭って、竹の籠? なんか、丁寧な暮らし意識高い系料理上手の人が使ってるイメージ。むしろ料理が面倒臭くなりそうだけど?!
肉まんとか、小籠包とか、翡翠餃子とかの手の込んだ中華料理に使うやつでしょ?
そのような料理ももちろんできますが、実は料理を超簡単にしてくれる、私たちの味方なんです!
せいろをオススメする理由は5つ。
- 簡単
- 美味しい
- 同時調理ができる
- 楽しい
- 離乳食(特にBLW)ができる
メリット① 料理も手入れも簡単にできる
蒸篭料理って、小籠包とか翡翠餃子とかに使うの? 私そんな、料理上級者のものなんて作れないーーー
実は、ほとんど「素材を切って入れて蒸すだけ」の超簡単な料理もたくさん作れるんです!
蒸篭で作れる簡単な料理の例
例えば、こんな料理が作れます。
①野菜と豚バラ肉を切って蒸すだけ

②鶏肉に切り込みを入れて蒸すだけ

③魚の切り身を野菜と一緒に入れて蒸すだけ

やる気がないときの蒸篭料理!
たまには気合を入れたものを作りたいとも思うけど…
気合の入れた料理もできますよ! 中華おこわを作ったら、おこわが苦手な夫に大好評でした!

他にも、肉まんや小籠包にもゆくゆくはトライしてみたいです。
蒸している間に他のことができる
炒め物は焦げるし、茹でるときは噴きこぼれる心配があるので、見張っておく必要があります。
でも、蒸し物はその場を離れていても大丈夫!
蒸している間に、他の物を作ってもいいし、片付けをしてもいいし、子供のお世話もできます!
ホットクックのように、「放ったらかし調理」ができます!
ただし、その場を離れるときはタイマーをつけることを忘れずに!
蒸篭のお手入れ
なんか、お手入れが面倒くさそう。毎日ホコリをとったりニスを塗ったり天日干ししたり…
そんなことはしないので大丈夫!
せいろのお手入れは超簡単。
洗剤を絶対使わずに軽く洗い、よく干すだけ!
以上!
干す場所は日陰でOK! 風通しが良ければ大丈夫です。
私は台所の網棚の上にそのまま置いています。
壁やコンロの上にフックを取り付け、そこに干している人もかなりいらっしゃいます。
メリット② 蒸篭を使うと料理が美味しくなる
簡単なだけでなく、味も美味しくなります。
電子レンジや茹でる方法と比べてみましょう。
蒸篭を使うと電子レンジより美味しくなる理由
温めるだけなら、別に電子レンジでもできない?
そうなのですが、電子レンジよりも味は確実に美味しい!
これには理由があります。
電子レンジは食材が元々持っている水分を振動させて加熱するので水分が飛んだりしますが、蒸篭は食材に、新たに水分を加えつつ蒸します。そのため、瑞々しくなるからです。
また、サツマイモやカボチャなど、デンプンを含む食材の場合は、55度〜65度が一番美味しくなる温度なのですが、この状態でいる時間は蒸篭の方が長いです。
この温度の間にどんなことが起こっているの?
β-アミラーゼという消化酵素が働いて、甘みを作ってくれるの!

電子レンジはあっという間にこのエリアを過ぎて加熱されるのに対し、蒸篭はこのエリアをゆっくりと抜け、長い間、たくさん甘みを作ってくれる、
そうすると、ホクホク甘くて美味しい! ということになるのです。
蒸篭を使うと茹でるより美味しくなる理由
お湯で茹でることもできるけど?
お湯で茹でると、実は素材の旨味がお湯に溶けてしまうんです!
野菜に含まれている水溶性の旨味は、茹でるとお湯に溶けてしまいますが、蒸篭はそのようなことなく、旨味をキープしたまま食べられます。
ただし! ほうれん草は例外的に、茹でてシュウ酸を取り除く必要があるので、蒸篭には不向きです。
なお、料理研究家の方の中には「蒸篭を使うと旨味が凝縮される」とおっしゃる方もいますが、私はその理屈が今ひとつ納得できないのでここでは挙げません。あくまで感覚的なものであり、科学的にはちょっと分からない。
これらの理由から、蒸篭は食材の味を最大限に引き出してくれるツールと言えます。
蒸しただけで立派な一品になってくれて、料理の手間も省ける!
メリット③ 同時に2品以上が作れる
蒸篭って二段くらいあるイメージだけど、それぞれの段で別の料理を作れるの?
もちろんです! だから同時調理はおてのもの!
主菜、副菜と複数料理を同時で作ることはしんどいですよね。
ですが、蒸篭だと簡単にできてしまいます。
私は二段の蒸篭を使っていますが、よくやるのが下段➡︎メインディッシュの肉や魚、上段➡︎シンプルな蒸し野菜
また、下のお湯を沸かす鍋も、レトルトのものを茹でることや、(量がかなり多いけど)スープ作りに使っています。

いっぺんにできると、時短にもつながるね!
そう言えば、点心のレストランなんかに行くと、小さい蒸篭が10段くらい?重ねられて蒸されているよね!
いいなー私、そういう所行ってみたい!
メリット④ 「映える」のでテンションが上がる
ここで、私の蒸篭料理の投稿で反響があったものをお見せします!

いいな! 肉巻きおいしそう! すごく手間をかけてそうだけど?
実は材料を切って肉で巻いて蒸しただけ! そんなに手をかけた料理ではありません。
蒸篭は見た目もかっこいい上に、食卓にそのまま出すことができるので、盛り付けをグレードアップしてくれます!
また、蓋を開けた瞬間に蒸気と食べ物の香りがホワーっと広がるのは、テンションが上がる!
料理は、食べるだけでなくて、目でも味わうものだと思うので、こういう「映えるしテンションが上がる」のって、大事です!
メリット⑤ 離乳食(特にBLW)も作れる

ただでさえ料理面倒なのに、大人の料理に加えて離乳食を3回も作らないといけないなんて! ノイローゼになりそう!
私は、夜ご飯の時に多めに野菜を蒸すだけで簡単に3食用意ができています!
通常の「ペーストにしてスプーンで食べさせる」離乳食の場合、野菜を蒸篭で加熱すれば、後は潰したり小さく切ったりするだけ!(特に、かぼちゃなど)
わざわざそれだけのためにお湯を沸かして茹でたりしなくても、蒸篭の隅に置いておくだけで大丈夫です。
というかちょっと引っかかったんだけど、「通常のペーストの離乳食の場合」っていうけど、ペースト以外の離乳食って、なに?
BLW離乳食です! 実は私はBLWで食べさせています。詳しくはこの記事を読んでみてね!

蒸篭でBLWをしていると、夜に野菜を多めに蒸しておき、それを翌朝・昼のBLWにも使うという、とてもシンプルなルーティンができます!
超楽チン! どんどんこのやり方を広めたい!
蒸篭の選び方

蒸篭って便利そう! でも種類が多そうで、何を買ったらいいか分からないなー
蒸篭に使われる材質は、杉、竹、桧(ヒノキ)、白木の四つです。
これらから、好みで選ぶと良いかと思います。
①杉の蒸篭
杉は一番安いです。木の香りもします。
「試しに使ってみたい」「長く使うかは分からない」という方にオススメ。
私は、メインの大きめの竹の蒸篭の次に、サブとして小さい杉の蒸篭がきになる! ちょこっとパンやソーセージを蒸すのに良さそうです。
②竹の蒸篭
私が使っているのが、中くらいの価格帯の竹の蒸篭です。
迷ったらこれで良いのではと思います。一番無難!
ただし、他の杉やヒノキみたく、木の香りを楽しむことはできませんが。
因みに、横浜中華街の照宝というお店で、B品を含め6000円弱で買いました!
照宝さんの蒸篭はプロも愛用するものなので、横浜にアクセスできる方はぜひ足を運んでみてください!
買いに行くついでにあるお店でご飯を食べたら、早速照宝さんの蒸篭が使われていました。多分、横浜中華街みんな使ってる…
③桧(ヒノキ)の蒸篭
桧は一番高級です。その分、ヒノキの香りも楽しむことができます。
④白木の蒸篭
これは照宝さんにしか売っていないようです。一応リンクを貼ります。
せっかくだから、私は桧の蒸篭にしようかなー。これを買えば完璧!
そうだ!一つ忘れてたことが!
蒸篭を買うならセットで買って!
蒸篭を買うときは、蒸篭用の鍋がない限りはぜひ、この蒸し板もセットで買いましょう!
これで、サイズを気にせず蒸篭が使えるようになります。
それに、私は鍋の直径と同じものを買ったはずなのに、上手く乗らなくて、最初はずっと斜めになった状態でした!
蒸篭が斜めに刺さってしまうと、熱くなったあと抜くのが大変! 涙。蒸し板はぜひ使いましょう。
蒸篭で蒸す時間
とは言え、どのくらいの時間蒸すのかよく分からないし、難しそう!
私はキリの良い時間で蒸すようにしています!
- 根菜 20〜30分
- 豚肉・牛肉・魚・かぼちゃ 15分
- 鶏肉 10分(後は余熱で)
- 青菜・ブロッコリー 強火で3分
これは一つの目安。もっと微細な味の違いを追求すれば、8分とかの数字が出てくるとは思います。
でも、毎日多くの食材をする上でそれは難しいので、シンプルに決めています。
最後に 蒸篭は育児の味方!

肉まんや小籠包といった、難易度高めの料理のイメージが強い蒸篭。
ですが、アナログなのにかかわらず手間いらず、しかも味もとっても美味しくできてしまう、子育ての味方です!
蒸篭の良さを広めたいので、今後もどんどん蒸篭について発信していきます! 最後まで読んでくれて、ありがとうございましたー!
物は試しに、一番安いらしい杉の蒸篭を取り寄せてみようかなー
せっかくだから、私は横浜商店街に行って、桧のいいやつを買ってみよう♪




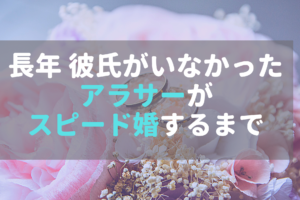




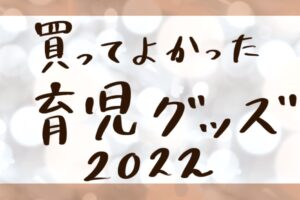

コメントを残す